|
|
・タッチ・センス (Touch Sens)
キーボードを押した強さを感知する機能。
鍵盤を押した速さを感知するものや、打鍵後に鍵盤を深く押し込む事により作動するもの、また Yamaha のオルガン YC-45D のように、鍵盤を左右に揺する事により作動するものもある。
これがあるキーボードなら鍵盤を弾いた強さに対応して音量や音色が変えられる。
|
|
・ダンパー (Damper)
ピアノの弱音ペダル。シンセサイザーのペダルでは,サスティン/ダンパー含めてダンパー・ペダル(実際にはサスティン・ペダルとして使用するのに)と呼んでいる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・DCO (Digital Controlled Oscillator)
デジタル技術の発達により,それまで電圧で制御していた発振器( VCO )をデジタル制御することが可能になり,登場してきたオシレターの名称。
DCOではピッチ・コントロールをデジタル信号で行い,それをアナログ信号に変換して VCF に送るものが多い。初期の DCO 搭載機種としては Roland の Juno-6 が有名。
|
|
・逓倍器(ていばいき)、マルチプライヤー(Multiplyer)
入力に入ってきた信号の周波数を2倍、4倍とX倍の周波数にする回路。シーケンサー等のクロックの速度を変更したり、入って来た音の音程を変えたりと、コントロール系にもオーディオ系にも使用可能。
その逆の分周器は、シンセサイザーでもよく使われる。ディバイダーの項も参照。
|
|
・ディバイダー(Divider)、分周器
日本語では分周器と呼ばれ、入って来た信号の周波数を 1/2、1/4、1/8 というように落としていく。
例えば 1/2 にセットされたディバイダーの入力に 440Hz の信号が入力すると、出力には 220Hz の信号が出て来る。つまり音程が1オクターブ下になる。
ディバイダーでは入って来た信号をカウントして、指定回数毎に出力の電圧を H にしたり L にしたりする事を繰り返す。このためディバイダでピッチを落としたサウンドの出力波形はみな矩形波になる。シンセサイザーのサブ・オシレター の波形に矩形波が多いのは、このためである。
また、オルガンでも一番上の1オクターブ分の発振器だけを作り、それをディバイダーで順次1オクターブずつ落として音源としている機種は非常に多い。
音程を変える以外のディバイダーの使い道として、クロック信号の分周がある。
例えば、16分音符で演奏している1台目のシーケンサーのクロックをディバイダーで半分に落とし、2台目のシーケンサーは8分音符のフレーズを演奏させる等の応用が考えられる。
|
|
・ディレイ (Delay)
遅れの意味。
ディレイ・ビブラートという使い方の場合はビブラートが遅れてかかり出す効果のこと。
また,エフェクトとしてのディレイは入力信号を時間的に遅らせること。遅らせる時間が短い(約20ミリ秒以下)場合にはフランジャー効果となり(正確にはLFOで遅延時間を揺らしてやる),時間が長い場合にはエコー効果となる。
最初はディレイ・ビブラート無しで、次にありで演奏してみる。
|
|
|
|
|
・デジタル (Digital)
段階的に変化する量のこと。すべてを数値として表現している。
|
|
・デジタル・オシレター (Digital Oscillator)
コンピューター等の数値計算によりデジタル的に信号を発生させるオシレター。
出力信号をアナログに変換しているものもあれば,数値データのまま次の処理(フィルタリングやエフェクト等)に送り出すものまで色々なものがある。
DCOの項も参照。
|
|
・デジタル・シーケンサー (Digital Sequencer)
コンピューターのメモリー上に演奏情報を記録し,それを再生するタイプのシーケンサー。
もっとも初期のタイプとして Oberheim のDS-2 や EMS のシーケンサー256 などがある。一般的なデジタル・シーケンサーとしてはローランドの "MC-8" や "MC-4" が有名。
|
|
・デシベル (Decibel)
電話関係で使われ始めた単位で,ベル(B)の 1/10。オーディオのレベルを表すのにも利用される。
10mWは1B(=10dB),100mWは2B(=20dB),1000mWは3B(=30dB)のように対数値をとる。アンプの増幅率計算などで,100倍の増幅率のアンプを2個つなげたとき,100×100=10000といった桁数が大きくなって計算しにくいときでもデシベルで表現してやると40dB(100倍)+40dB=80dB(10000倍)といったように簡単に表現できる。
シンセサイザーにおいてデシベルという言葉をもっともよく耳にするのがVCFの特性に関してであろう。VCFのきき具合は12dB/octまたは24dB/octというように書かれている。これは実際には-12dB/oct,-24dB/octと書くのが本当であり,フィルターのきき具合の指標となる。
-12dB/octではカットオフ・フレケンシーのポイントから1オクターブ上の周波数帯域で(ローパス・フィルターの場合)音量レベルは 1/4 に,-24dB/octでは1/16 になる。カットされる度合いが大きいほど音色は極端に変化するわけである。ちなみに通常のステレオ・アンプのトーン・コントロールは-6dB/oct,またホワイト・ノイズからピンク・ノイズを作り出すフィルターでは-3dB/oct程度の特性である。
ポールの項も参照。
|
|
・デチューン (Detune)
VCO( VCF のカットオフ・フレケンシーで使われる場合もある)のピッチの微調整。
または1つの VCO に対して,他の VCO のピッチを微妙にずらしてやること。
最初はデチューンの幅を狭く、次に広くしたサウンド。
|
|
・デプス (Depth)
深さの意味。
シンセサイザーではモジュレーションをかける度合いのことをデプスと呼んでいる。たとえば VCO にかけるビブラートの深さを調整するボリュームはビブラート・デプスという名前がついているのが普通である。
|
 |
|
・デューティー・サイクル (Duty Cycle),またはデューティー比
パルス波の波形の上下の比率(T2/T1)。
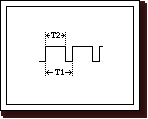
デューティー比を LFO で変化させるのが PWM(パルスワイズモジュレーション)である。ごく一部のシンセで PWM をデューティー・サイクルと表示しているものもある。パルス・ワイズの項も参照。
|
|
・デュオフォニック (DuoPhonic)
初期のシンセサイザーのうち,押した鍵盤の中の最高音と最低音の 2音を出すことができるものがあり,これをデュオフォニックと呼んでいた。
"Arp の Odyssey" や, MOOG のSonicSixがこれにあたる。
デュオフォニックの演奏可能なシンセサイザーのサウンド。
|
|
・デュアル・ボイス (Dual Voice)
デュオフォニックの項参照。
|
|
|
|
・トゥー・ポール (2-Pole)
フィルターの特性の表わし方。
1ポールあたり -6dB/oct の特性なので,2ポールのものは -12dB/oct の特性となる。フォー・ポールの項も参照。
12dBと24dBの特性をもつフィルターで、それぞれ2回ずつカットオフ・フレケンシーを動かしてみる。次に同じ事をレゾナンス5でやってみる。
|
|
・トライアングル・ウェーブ (Triangle Wave)
三角波の項参照。
|
|
・トラッキング (Tracking)
入力した CV に対して,接続先の機能をどの程度追従させるかを決めること。
たとえば VCF の場合,キーボード CV を VCF に送り,カットオフ・フレケンシーを VCO のピッチに追従させる度合いとなる。これらはフィルター・キーボード・トラッキング,キーボード・フォローなどと言った名称で呼ばれる。追従の度合いが小さければ弾いた音域によって音色に違いが出てくる。
最初フィルター・キーボード・トラッキングを0で、次に10で音階を演奏。
|
|
・トラック (Track)
マルチ・トラック・レコーダーやシーケンサーで音を記録できる場所の事。
|
|
・トラベラー (Traveler)
KORG (旧京王技研)の初期型シンセサイザーに使用されていた VCF のカットオフ・フレケンシーの名称。
"Mini Korg 700 (S)" や "800DV (Maxi Korg)" ではハイ/ローの2種のトラベラーが,"マイクロプリセット" 等ではローのみのトラベラーがついていた。
また、この機能だけを抜き出したギター用のペダルエフェクターも存在した。レトロ広告のエフェクターの項参照。
トラベラーのHigh/Lowを動かしてみる。
|
|
・トラベラー・ビブラート (Traveler Vibrato)
KORG (旧京王技研)の初期型シンセサイザーに使用されていた VCF・モジュレーションの名称。
LFO の出力電圧を VCF に送って得られる効果のこと。他機種のグロウルにあたる。
トラベラー・ビブラートをかけながらトラベラーのHigh/Lowを動かしてみる。
|
|
・トランジェント・ジェネレーター (Transient Generator)
エンベロープ・ジェネレーターの別称。エンベロープ・ジェネレーターの項を参照。
|
|
|
|
|
・トリガー (Trigger)
引きがねの意味。通常鍵盤を押した瞬間に出力される短い信号,またはそれに似た信号もさす。
ゲート信号と似ているが,ゲートの場合,鍵盤を押している間ずっと出力されるのに対してトリガーは瞬間だけ出力される点が違う。この信号は エンベロープ・ジェネレーターを動かしたりシーケンサーを走らせるきっかけの信号として利用する。メーカーによってはゲート信号をトリガーと称している場合もある。
エンベロープ・ジェネレーターをゲート+トリガーの信号で動かすと,音程が変わる度にエンベロープ・ジェネレーターが再起動する。
|
|
 |
・トレモロ (Tremolo)
LFO などで VCA をコントロールし,一定間隔で音量を変化させること。
Amplitude Modulation(A.M.)ともいう。A.M. の項も参照。
トレモロのサウンド。
|
|
|
|
|
・トーン・ホイール(Tone Wheel)
古いハモンドオルガンの音源として使われている仕掛け。
一定速度で回転する長い棒に直径2インチの歯車状のホイールが96個取り付けられている。各ホイールの縁は磁力がありギザギザ模様が刻まれている。このギザギザにピックアップを近づけ、磁力の変化を電流に置き換えて音源の信号としているのが、トーン・ホイールである(下記写真参照)。
トーン・ホイールに刻まれたギザギザの数が多ければ得られる音程は高くなる。ギザギザの数が倍違うトーン・ホイールは1オクターブ違う音程を作る事ができる。
トーン・ホイールは一定速度で回転しているが、鍵盤を押さえながら電源をオン/オフすると全体の音程がベンドする。これを利用して演奏していたのがキース・エマーソンであった。古いハモンド・オルガンでは電源投入時にモーターの回転を上げるためにセルスイッチが付いており、自動車のセルのように回転が安定するまでセルスイッチをオンにする必要があった。

オルガン内部のトーン・ホイール
>ハモンドオルガンの古いカタログへ。
|
|