|
|
・ラグ (Lag)
遅れるといった意味。
シンセサイザーでは入力電圧の変化をなめらかにするモジュールをラグ・プロセッサー(またはインテグレーター、Doepfer のモジュールでは Slew Limmiter)などと呼んでいる。VCO に送るキーボード CV をラグ・プロセッサーに通せばポルタメントをつけることができる。ラグ・プロセッサーではラグ・タイムのボリュームが通常のポルタメント・タイムのボリュームに相当する。
また,サンプル&ホールドにはラグ・タイムのボリュームがついているものもあり(ARP の"Odyssey" ),これを上げればサンプル&ホールドの段階的な電圧出力にポルタメントをつけなめらかな電圧変化の出力を得ることができる。
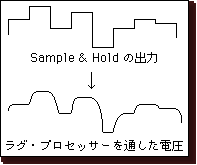
ランダム・ノートを演奏するサンプル&ホールドのLAG TIMEボリュームを上下する。
|
|
|
|
|
・ラダー (Ladder)
梯子(はしご)の意味。
初期の MOOG や ARP のフィルターでは梯子のように何段もトランジスターをつなぎ,VCF を作っており,これをフィルター・ラダーなどと呼んでいた。この方式は MOOG の特許となっており,"Minimoog" などの太いサウンドを出す要(かなめ)と言われている。現在では特許期限は切れオープンなものとなっている。
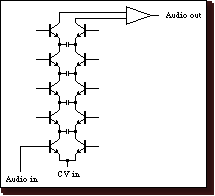
System-700 のフィルターと Moog のラダー・フィルターに鋸歯状波を送り、2回ずつカットオフ・フレケンシーを上下に動かす。最初は単音、次にフレーズによる演奏。一般的に言われている Moog サウンドの良さが、ラダー・フィルターによるものだけではないことがわかるだろう。
|
|
・ランダム(Random)
乱数、メチャメチャなと言った意味。
アナログシンセサイザーでは、サンプル&ホールドによるランダム・ノートを意味する事が多い。
|
|
・ランダム・ノート(Random Note)
初期のアナログシンセサイザーによく搭載されていた機能。ランダム・ノート・スイッチをオンにすると、一定間隔でメチャメチャな音程が出力される。
サンプル&ホールドの項も参照。
ノイズをサンプリングしてランダムなピッチの電圧を作り、それをVCOに送ってランダム・ノートを演奏させる。
|
|
・ランプ・ウェーブ (Ramp Wave)
鋸歯状波のこと。踞歯状波の項参照。
|
 |
|
|
|
・リシンセシス (Resynthesis)
音の倍音構成を解析し,その結果を元に倍音加算方式や FM 方式で解析した元の音と似た音を新たに作り出す事。
Fairlight や Synclavier のリシンセシス機能が有名。
ブラスのサウンドを倍音加算によるリシンセシスで合成してみる。最初が元の音、次に同じフレーズをリシンセシスした音で聞く。
マリンバのサウンドを倍音加算によるリシンセシスで合成してみる。最初が元の音、次に同じフレーズをリシンセシスした音で聞く。
ブラスのサウンドをリシンセシスしたものの波形とサウンドを1ステップずつ聞いてみる。
横方向に1〜32まで表示されているのが倍音フェーダー。
音の出始めは多くの倍音を含んでいるが、徐々に同じような倍音構成の鋸歯状波サウンドが持続するようになる。
マリンバのサウンドをリシンセシスしたものの波形とサウンドを1ステップずつ聞いてみる。
音の出始めは多くの倍音を含んでいるが、すぐに高次の倍音が消え、サイン波に近い音になってしまう。
また9倍音が強くあらわれるのが特長で、シンセサイザーでマリンバの音を作る場合にもロング・ディケイの基音に、ショート・ディケイの9倍音(基音ドに対して3オクターブ上のレ)を足すと心地よいサウンドが作れる。
|
|
・リピート (Repeat)
同じ鍵盤を何度も繰り返し演奏すること、または同様のことを行う機能をいう。
リピート・スピードを変えながら演奏。
|
|
・リニア (Linear)
直線の意味。
VCO で CV に対して出力されるピッチの直線性の良さはピッチの安定度に影響する。安定したピッチの VCO をリニアリティがいい,などと言う。
VCO のピッチは CV:オクターブで考えればリニアな特性だが,CV:周波数で考えるとエクスポネンシャルなカーブとなっている。
また VCA の特性切り替えのリニアでは音量の変化幅と電圧の関係は 10%/1V となる。この特性は一般的なシンセサイザーのVCAに利用されているが,モジュラー・シンセサイザーなどでは特性をエクスポネンシャルにして使用することもできる。
エクスポネンシャルの項も参照。
リニアリティの悪いVCOの例。
|
|
・リバーブ (Reverb)
残響のこと。
音が壁等に乱反射して複雑に残った状態。普通の人間はたいがいの音を,このリバーブと一緒に聞いて認識している。初期のシンセサイザーでは,スプリング・リバーブのユニットが内蔵されているものもあった。
ディレイの項も参照。
リバーブのサウンド。
|
|
・リボン (Ribbon)
帯状の意味。
MOOG やヤマハのシンセサイザーに採用されているピッチ・ベンダー。指で触った位置に対応して電圧が出力され,上の方を触れば高い電圧が,下の方なら低い電圧が出力される。MOOG ではリボン・コントローラーとして別売りのユニットも発売されていた。キース・エマーソンがステージでお尻に擦りつけてパフォーマンスしていたのが有名。
CV 出力のできる単体製品は VCO だけでなく、色々なモジュールのコントロールに使用できる。
リボン・コントローラーをお尻に擦り付けるエマーソンが見れます
|
|
・リリース (Release),リリース・タイム (Release Time)
音の余韻。
エンベロープ・ジェネレーターでゲート信号がなくなった後に電圧が 0V になるまでにかかる時間。エンベロープ・ジェネレーターの図参照。
リリース・タイムを0から徐々に上げていったサウンド。
|
|
 |
・リング・モジュレーター (Ring Modulator)
シンセサイザーのモジュールの1つ。
2つの入力があり,出力にはその2つの和と差の周波数の信号が出てくる。これを利用すると非整数次の倍音を作り出すことができる。鐘の音を作るときなどに使用する。
リング・モジュレーターに2つのVCOのサイン波を送り、両方のピッチを変えながら演奏。
|
|
|
|
・レゾナンス (Resonance)
共振/共鳴の意味。
VCF についており,カットオフ・フレケンシーの位置(カットオフ・ポイント)の周波数を強調して音色にクセをつけるもの。ボリュームを上げていくと VCF が自己発振するものとしないものがある。このレゾナンスの自己発振を音源として利用することも可能である。
機種によって Res と略されていたり、Q と書かれていることもある。
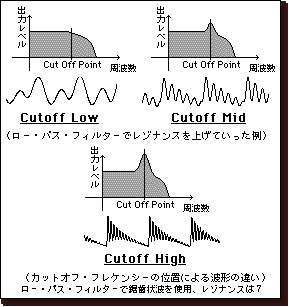
レゾナンスを上げたVCF(ロー・パス)に鋸歯状波を送り、カットオフ・フレケンシーを上下する。
|
|
・レゾナント・フィルター (Resonant Filter)
レゾネーターの項参照。
|
|
・レゾネーター (Resonator)
特定(固定または可変)の共振周波数をもつフィルターの事。
|
|
・レンジ (Range)
範囲/音域の事。
一般的には VCO のオクターブ音域切り替えスイッチ。フィート・スイッチ等と呼ぶ事もある。フィートはパイプオルガンのパイプの長さに由来した言葉で、長いパイプの方が音程が低い。したがってフィートの数字が大きい場合、音域は下がる。
シンセサイザーによっては VCF のカットオフ・フレケンシーの有効範囲の切り替えスイッチや,モジュレーションなどの深さを変えるボリュームもレンジと呼んでいる。
フィート・スイッチを16’/8’/4’/2’に切り替えたサウンド。
|
|
|
|
・ロー・ノート・プライオリティ (Low Note Priority)
低音優先。鍵盤を複数押さえた場合,その中の最低音を発音する方式。
"Minimoog" など,初期のシンセサイザーにはこのタイプのものが多かった。
|
|
・ローパス・フィルター (Low Pass Filter)
VCF で最も一般的なフィルターのタイプ。
カットオフ・フレケンシーで設定したよりも上の周波数帯をカットし,柔らかい音にする。
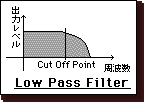
VCF(ロー・パス)に鋸歯状波を送り、カットオフ・フレケンシーを上下する。
ロー・パス/バンド・パス/ハイ・パスのサウンドを順番に聞いてみる。
|
|