|
|
・アタック(Attack),アタック・タイム(Attack Time)
音の出始めの部分。
エンベロープ・ジェネレーターにゲート信号が送られてから,出力電圧が最大値に達するまでの時間。下図参照。
通常のシンセの接続では、鍵盤を押してから、出てくる音の音量が最大になるまでの時間をさす事が多い(モジュラーシンセでは、そう言い切れない)。
一般的な解釈の「アタック感」とは語意が違うと思われるので注意が必要。
古いシンセサイザーや電子オルガンのアタック機能は、現在のシンセではディケイ(Decay、下図参照)である場合が多い。1975年前後を境に、この言葉の定義がはっきりし始めた。よってそれ以前の楽器では、機能にバラツキがある。
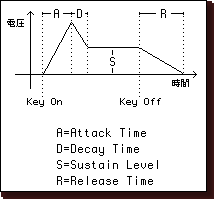
アタック・タイムを徐々に上げていく。
|
|
・アッテネーター (Attenuator)
減衰器の意味。
入力信号のレベルを調整するボリューム・ユニットのこと。
|
|
・アディティブ・シンセシス (Additive Synthesis)
倍音加算の項参照。
|
|
・アナログ (Analog)
連続的に変化する量のこと。
デジタル と対比して使われる,
アナログの波はある部分をどんどん拡大して行っても、やはり連続的な曲線変化をしている。しかしデジタルは拡大して行くと、曲線ではなく階段状に変化している事が分かる。デジタルの解像度をどんどん上げて行けば、アナログに近くはなるが、決してアナログと同じにはならない。
デジタルの項も参照。
|
|
・アナログ・シーケンサー (Analog Sequencer)
シーケンサーの項参照。
|
|
・アフター・タッチ (After Touch)
鍵盤を押した後に、鍵盤をどの位強く押し込んだか。
キー・プレッシャー、フォース・センサー等色々な呼び方があった。現在の Midi 規格ではアフター・タッチは、はっきりとした定義があるが、アナログ・シンセ時代は結構適当だった。
最初はピッチ・ベンド(アップ)を、次にビブラートの深さをアフター・タッチでコントロールする。
|
|
・アマウント (Amount)
エンベロープ・ジェネレーター等からの電圧のかかり具合。
例えば、Minimoog の VCF セクションにある「Amount of Contour(アマウント・オブ・コントゥア)」のボリュームは VCF にかかるコントゥア・ジェネレーターの電圧の度合いを決めるためのもの。
|
|
|
|
|
・アルペジェーター (Arpeggiator)
押さえた和音を一定のリズムで分散和音にして自動演奏する機能。
アルペジオのパターンは上行や下降、ランダム等機種によってまちまちである。
アルペジェーターのサウンド。
|
|
・アンサンブル(Ensemble)
複数の同じ楽器が鳴った時に、各楽器の音程の違いから起こる音の広がりや厚さの事を指す。
オーケストラのストリングスセクションのような効果が有名。
コーラスの項も参照。
|
|
・アンチ・ログ・アンプ (Anti Log Amp)
1V/1oct 規格のシンセでは,VCO にかける CV が1V変わるごとに出力の音程が1オクターブ変わるように設計されている。この場合 CV:オクターブという考え方をすれば 1:1 の正比例であるが,正確には CV:周波数(振動数)となる。周波数は音程が 1 オクターブ変わると 2 倍(または 1/2 倍)変わるため,実際には CV に対して対数の値となる(下図のようなカーブになる)。
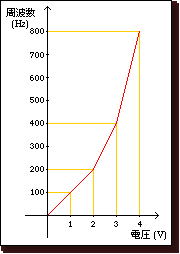
たとえば 1V で 100Hz の周波数で発振する VCO があった場合,CV を 2V にすれば周波数は 200Hz,3V なら 400Hz,4V では 800Hz といったように,CV:周波数は対数カーブをとることになる。
VCO 本体はこのような対数カーブではなく,CV:周波数が 1:1 になるよう設計されているため,これを対数カーブに変換してやる必要がある。この変換を行うのがアンチ・ログ・アンプである。このように 1V/1oct 仕様のシンセでは,アンチ・ログ・アンプが VCO や VCF の CV インプット部分に使用されている。
アンチ・ログ・アンプは 1970 年代の技術では安定させるのが難しかった(CV が高くなるほど出力の変化幅が極端に大きくなっていくため)。初期のシンセで 1V/1oct 規格にのっとったもののピッチが不安定になりやすかったのは,これが原因となっている場合が多い。逆に 1V/1oct の規格に準じていない機種は音程の安定度が高かったのも,この理由による。
アンチ・ログ・アンプの不安定さは温度に起因する部分が多かった。このため使用する半導体を最初からヒーターで暖めてしまう恒温槽付のオペ・アンプなどが開発された。
|
|
・アンプ またはアンプリファイア(Amplifier)
増幅器の意味。
ギター・アンプ、ステレオ・アンプ等の総称。
|
|
・アンプリチュード (Amplitude)
振幅の意味。
信号の大きさのこと。
|
|
・アンプリチュード・モジュレーション (Amplitude Modulation)
A.M. の項参照。
|
|
|
|
|
|
|
・位相
波形のずれ具合。
下図で位相が90度ずれるとは元の波形に対し,1/4 波形分だけ波がうしろにずれることになる。また位相が180度ずれるという場合には、波形は元の波に対して上下が逆になる(これを逆相という)。
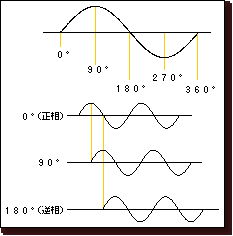
これらのずれを LFO を使って順次動かしてやると,スピーカーが回ったような効果になる。フェイズ・シフター(フェイザーまたは単にフェイズともいう)では,このように入力波形の位相をLFOで揺らして音が回ったような効果を出す。
フェイザー・オフからオンへ。そして、徐々にレゾナンスを上げていく。
|
|
・インターフェイス (Interface)
外部との情報(データ/コントロール電圧等)をやりとりする窓口部分または,やりとりの方式をさす。
インターフェイスの方式が違うシンセサイザーは接続してもうまく音を出すことができない。
またシンセサイザーのインターフェイス・ユニットでは外部の信号(マイクや楽器)を接続し,その信号のエンベロープ電圧やピッチ電圧を検出し出力する。
|
|
・インテグレーター (Integrator)
積分器。
ローランドのSystem-700などにある機能で,入力信号の電圧変化を緩やかなものに変換する。キーボード CV を接続すれば CV にポルタメントを付加することができる。ラグの項も参照。
ランダム・ノートを演奏するサンプル&ホールドにポルタメントを付加してみる。
|
|
・インバーター (Inverter)
入力信号の極性を反転させる装置。
プラスの電圧はマイナスに,マイナスの電圧はプラスになる。キーボード CV をインバーターに通して VCO に接続すると上下逆の音階で演奏ができる。
このやり方による演奏はウェザー・リポートのジョー・ザビヌルがやったので有名。
通常のピッチのサウンドを左に、
キーボードCVをインバーターに入れてピッチを反転させたサウンドを右にして演奏。
下図の例では、0Vから上昇するタイプの鋸歯状波をインバーターに通して、0Vから下降する鋸歯状波に変えている。
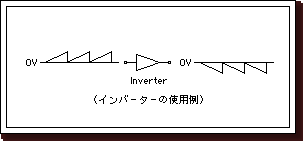
|
|
|
|
・ウェーブ・テーブル (Wave Table)
コンピューターのメモリーに,多数の波形をデジタル・データとし登録したもの。
それを順次読み出してくることにより音を作る。これをうまく利用するとデジタルでありながらアナログ的な音源を作ることができた。"PPG の Wave 2.2 / 2.3" で採用され有名になった。
☆下図のテーブルの波形を1→5の順に読み出せばパルス・ワイズの変化したのと同様の音色をえられる。
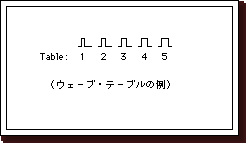
PPG のウェーブ・テーブルの1〜20までをマニュアルでゆっくり切り替えながら聞いてみる。
テーブルの1〜20をエンベロープ・ジェネレーターのアタックとディケイを使ってオートで動かす。
徐々にアタックを短くしていき、フレーズを弾いてみる。
隣どうしのWaveの波形が極端に違ったテーブルをエンベロープ・ジェネレーターで動かしながら
聞いてみる。
|
|
・ウェーブ・フォーム (Wave Form)
波形の項参照。
|
|
|
|
・AR
"Arp Odyssey" 等に搭載された簡易エンベロープ・ジェネレーター。
"アタック(Attack)” ・"リリース(Release)” の略で,エンベロープ・ジェネレーターの最も簡単な構成の1つ。下図参照。
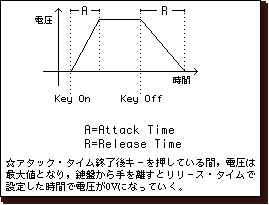
|
|
・A.M.(Amplitude Modulation)
音量(振幅)に対するモジュレーションのこと。
一般的には LFO の電圧を VCA に送りモジュレーションをかけることをさす。このとき,LFOの周波数が低く(一般的には20Hz以下),その波形がサイン波ならトレモロがかかることになる。
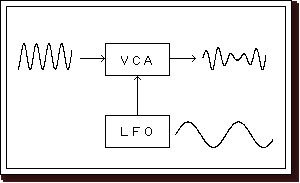
サイン波のレベルを別なサイン波でコントロールしてA.M.効果を得る。モジュレーションをかけるサイン波のスピードを徐々に早くしていき、リング・モジュレーターの効果を出してみる。
|
|
・エクスポネンシャル (Exponential)
指数関数の意味。
入力が小さいときには出力の電圧はそれほど変わらないが,入力が大きくなるにつれ出力の変化幅も極端に大きくなっていくカーブ。
通常シンセサイザーで、音程や音量は入力に対して出力が 1:1 の割合で動いているように見えるが,実際にはエクスポネンシャル・カーブを描くように内部でコントロールされている。
たとえば VCO では入力電圧に対する出力の音程の比は 1V/1oct の正比例であるが,これを周波数で表すとエクスポネンシャルなカーブとなる。1Vで100Hzの出力なら2Vで200Hz,3Vで400Hz,4Vなら800Hzという関係になっている。
また,人間が聴感上で感じるピアノ/フォルテ等の関係も数学的に表すとエクスポネンシャルなカーブを描いている。
さらに VCA の特性でエクスポネンシャルといった場合には,出力レベルとコントロール電圧の関係が10dB/1Vとなる。このカーブでは音量はコントロール電圧に対して極端に変化する。パーカッシブなサウンドや,シーケンサーによる抑揚コントロールを行う場合には,エクスポネンシャルな特性のVCAを利用することが多い。リニアの項も参照。
|
|
|
|
|
・A/Dコンバーター(A/D Converter)
Aはアナログ,Dはデジタルの略。
アナログの連続的な信号(波形やコントロール電圧等)をコンピューターで使用するデジタル・データに変換する装置のこと。その逆の機能をもつのがD/Aコンバーターである。
|
|
・エコー (Echo)
音が繰り返されながら消えていくタイプの残響効果。
音の繰り返しがはっきりしている場合エコー,全体がつながったように聞こえるのがリバーブと呼ばれているが,70年代以前にはこの両方を一緒にしてエコーと呼ぶことが多かった。
現在ではディレイ(Delay)と呼ばれる事の方が多い。
エコーのついたシンセサイザー・サウンド。
|
 |
|
・S/H
Sample & Hold(サンプル&ホールド)の略。
サンプル&ホールドの項参照。
|
|
・S-Trig(エス・トリガ)
古い Moog や Korg のシンセサイザーに使用されているゲート/トリガのタイプ。S は Switch の略で、スイッチ・トリガとも言われる。Gate、V-Trig も項を参照。
|
|
・FSK (Frequency Shift Keying)
エフ・エス・ケーと発音。初期のデジタル・シーケンサー("ローランド MC-8" 等)の同期信号や音色メモリー・データのテープへの記録に使用された方式。
離れた2つの音程を利用してデータを音程化し,テープに記憶する。同期信号に使用した場合,時間情報は含まれない。したがって曲の途中からスタートしてシーケンサーの演奏を同期させるということはできない。長い曲のエンディングのたった1個の音でも曲の頭から同期させて演奏させなければならなかった。
FSKフォーマットによる、MC-4 のシンク信号。テンポ・ボリュームを徐々に上げていく。
|
|
・FFT (Fast Fourier Transform)
高速フーリエ変換の意味。フーリエ変換の項参照。
|
|
・F.M.(Frequency Modulation)
周波数に対するモジュレーションのこと。
一般的には LFO の電圧を VCO に送りモジュレーションをかけることをさす。このとき,LFO の周波数が低く(20Hz以下),その波形がサイン波ならビブラートがかかることになる。ヤマハのDXシリーズやシンクラビアではこのFMをLFOではなく,もっと高い周波数の信号でモジュレーションし,音程ではなく音色を変えて音作りをしている。これを FM 音源と呼び、日本語では倍音乗算方式という(あまり使われない言葉である)。
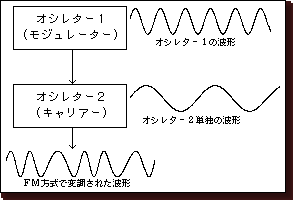
アナログ・シンセによるFM音源のシミュレートは"System-700 の項で紹介している" ので参照のこと。
キャリアーにかけるモジュレーションを徐々に深くしていく。次にモジュレーターのスピードを早くしていく。さらにモジュレーターの信号をVCAとエンベロープ・ジェネレーターでコントロールして、アナログFM音源サウンドを作ってみる。
|
|
・FVコンバーター (Frequency To Voltage Converter)
マイクやラインから入力された信号の周波数をシンセサイザー用のピッチ CV に変換する装置。
|
|
|
|
|
・MG
Modulation Generator の略。KORG 独自の言い方である。モジュレーションの項参照。
|
|
・LED
Light Emitting Diodeの略。発光ダイオード。
エル・イー・ディーまたはレッドと発音。シンセサイザーの表示灯として広く利用されている。LED 登場前のアナログ・シンセサイザーの表示灯には豆電球やネオンランプが使用されていたが、反応速度が遅かったため、LFO の発振周波数を視認するような事には利用できなかった。
|
|
・LFO
ロー・フレケンシー・オシレター(Low Frequency Oscillator)の略。低周波発振器のこと。
LFO ではビブラートやグロウル等に利用する周波数の低い信号を作り出す。たとえばLFOで作ったサイン波を VCO に送ればビブラート効果, VCF に送ればグロウル効果,VCA に送ればトレモロ効果となる。
|
|
・エンファシス (Emphasis)
レゾナンス(Resonance)と同じ。
MOOG のプロダクトではVCFのレゾナンスをエンファシスと呼んでいる。レゾナンスの項参照。
|
|
|
|
|
・エンベロープ (Envelope)
音が出てから消えるまでの音量(または音程や音色)変化のカーブのこと。日本語では包絡線という。
|
|
・エンベロープ・ジェネレーター (Envelope Generator)
エンベロープ・カーブをもった電圧を作り出すモジュールのこと。
このモジュールの出力電圧を VCO につなげば音程が、VCF につなげば音色が、VCA につなげば音量がエンベロープ・カーブにしたがって変化する。またこの電圧をシーケンサーにつなげば演奏速度の変化するシーケンスパターンを作る事が出来る。応用の範囲は色々。
一般的なシンセサイザーは楽器音のもつ最も代表的なエンベロープを作れるよう以下の4つのパラメーターが調整できるようになっている。
A=Attack:楽器が鳴りはじめてから(キーボードを押してから)その音量が最大点に達するまでの時間。
D=Decay:アタック以後に楽器の音が減衰していくまでの時間。
S=Sustain:楽器演奏中の持続音量レベル。
R=Release:楽器の演奏をやめてから(キーボードから手を離してから)音が完全に消えるまでの時間。
これらの頭文字をとってエンベロープ・ジェネレーターは ADSR とも呼ばれる。また,ADSR の簡易版 AR や,更に複雑なエンベロープを作れる機種もある(ヤマハの シンセサイザー等)。
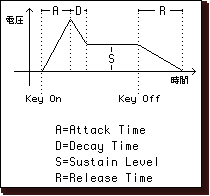
|
|
・エンベロープ・ディテクター (Envelope Detector)
“エンベロープ” 検出器の意味。
入力信号(マイクの音など)に信号が来るとトリガーやゲート信号を出力する機能をもつ。細かくいえば,ゲート・ディテクターの方が正しいかも...
|
|
・エンベロープ・フォロワー (Envelope Follower)
外部入力につながれたオーディオ信号の音量 “エンベロープ” ・カーブをエンベロープ電圧として出力する機能。入力に大きな音が入ってくれば高い電圧が、小さな音が入ってくれば低い電圧が出力される。
シンセサイザーのインターフェイス部には欠かせない機能である。
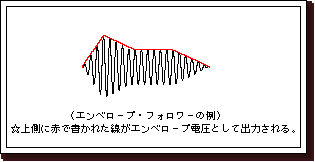
|
|
|
|
・オシレター (Oscillator)
発振器。
シンセサイザーの音源部分。アナログ・シンセサイザーでは、このオシレターが電圧で制御されているわけである。
|
|
・オーディオ信号 (Audio Signal)
音として耳に聞こえる電気信号のこと。
通常,耳には1秒間に20回(20Hz)〜2万回(20KHz)までの振動が聞こえていると言われている。実際に音程として認識されているのは 40Hz〜8KHz あたりまで(個人差あり)で、それ以上は音色の違いとして感じられている。実は 20KHz 以上の音も聞こえている、というのが現在の一般常識で、ハイエンドオーディオでは 48KHz〜96KHz まで再生できるオーディオ機器も販売されている。
|
|
・オート・グライド (Auto Glide)
鍵盤を押すたびに,弾いた音程の少し下(通常は半音くらい)から音程がゆっくり弾いた鍵盤に移動していく効果。”エンベロープ・ジェネレーター” の”ディケイ(Decay)” を短めにセットし、その出力電圧を”インバーター” で上下逆にして “VCO” に送ると、この効果を作る事が出来る。
オート・ベンドと言う機種もある。
ブラス系の音を作りでは、2つの “VCO” をユニゾンにし、片方の VCO に変化時間の早いオート・グライドをかけるのが一般的な手法である。
オート・グライドのサウンド。最初、オート・グライドをオフ、次にオンにして演奏。
|
|
|
|
|
・オーバートーン (Overtone)
倍音の項参照。
|
|